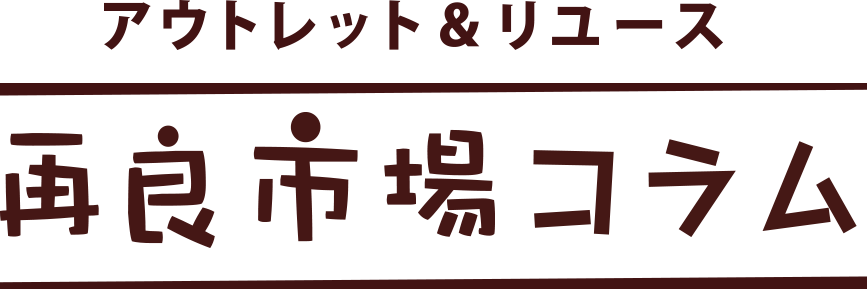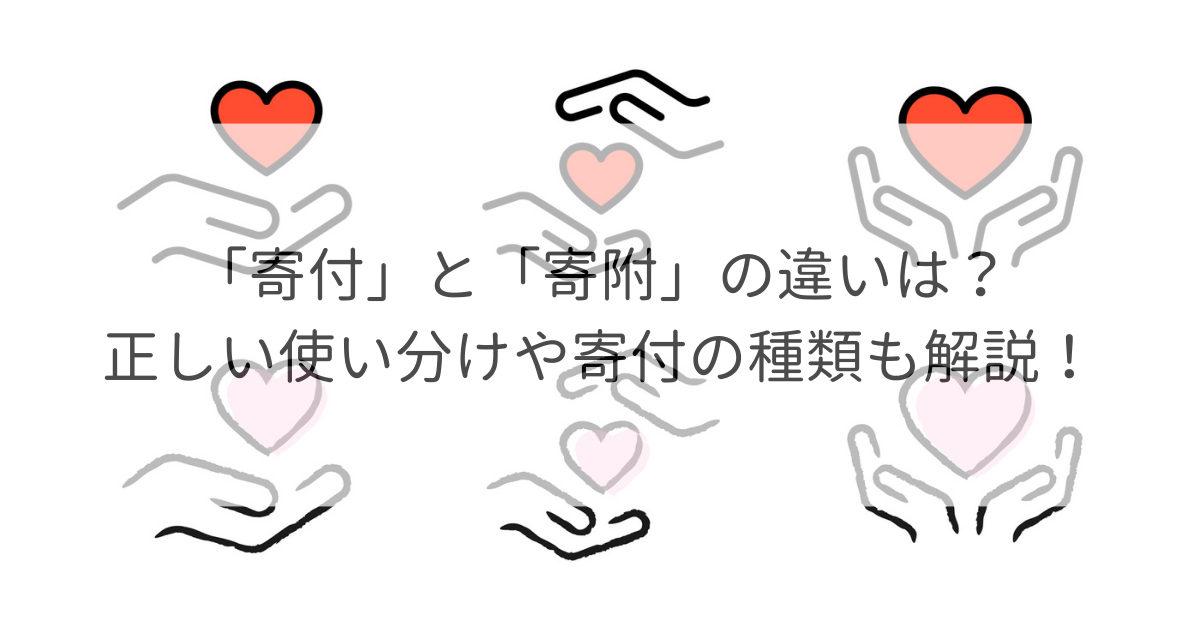「寄付」と「寄附」という二つの言葉は、同じ読みながら表記が異なるため、どちらを使えばよいか迷ったことのある方も多いでしょう。実際には意味は同じですが、使われる場面によって表記が分かれるのが一般的です。
そこでこの記事では、両者の使い方や似た言葉との違いなどをわかりやすく解説します。
さらに、金銭以外の寄付の形についても触れるので、社会貢献の幅を広げるヒントとしてぜひ参考にしてください。
「寄付」と「寄附」の違いは?
「寄付」と「寄附」は、どちらも「きふ」と読み、基本的には同じ意味を持ちます。
しかし、二つの表記が存在するため「どちらを使うのが正しいのか」と疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
実際は厳密なルールがあるわけではなく、文章が書かれる場面や文脈によって慣習的に使い分けられているのが実情です。
まずはこの違いを押さえておくと、文章を書く時などに迷わなくなるでしょう。
意味は同じでも使う場面に差がある
「寄付」と「寄附」はどちらも「お金や物を無償で差し出し、社会や他者に役立てること」を意味しており、本質的な違いはありません。
したがって、どちらの表記を使っても意味が変わることはなく、誤用とされる心配もないでしょう。
ただし、実際の使われ方を見てみると、文章の種類や状況に応じてどちらか片方が選ばれる傾向があります。
つまり、意味は同じでも場面ごとに表記が分かれているというわけです。
公用文では「寄附」・日常では「寄付」が一般的
日常生活で目にする機会が圧倒的に多いのは「寄付」です。新聞や雑誌、ニュースサイトやSNSの投稿でもほとんどがこの表記で、一般的な表現として定着しています。
一方、自治体や税制関連の文書では「寄附」と表記されることが多い傾向です。
例えば、確定申告の「寄附金控除」や自治体の案内など、公的な制度に関する文章では「寄附」が用いられるのが慣例となっています。
つまり、日常では「寄付」、公的文書では「寄附」と整理して覚えておくと、場面に応じて迷わず使い分けられるでしょう。
公的な書類で「寄附」が使われるのは制度上の名残
自治体や税金に関する書類に「寄附」という表記が使われ続けている理由は、制度的な背景によるものです。
戦後の漢字表記の改定で「付」が常用漢字に採用された一方、法律や制度に関わる文言は従来の表記を引き継ぎました。その結果、「寄附」という書き方が現在も公式な書類に使われているのです。
確定申告で用いる「寄附金控除」や、自治体の公文書に登場する「寄附」の文字はその典型例だといえるでしょう。
参考:文部省 用事用語例
「寄付」と似た言葉の違い
「寄付」という言葉に似た表現はいくつかあり、「募金」「義援金」「寄贈」などは特に混同されやすい用語です。
意味を正しく理解していないと誤解を生む可能性があるため、それぞれの違いを整理しておきましょう。
「募金」はお金を集める方法のひとつ
「募金」とは、不特定多数の人から少額ずつお金を集める行為を指します。
街頭で箱を持って立つ募金活動や、コンビニのレジの横にある募金箱などが代表例です。
募金で集まったお金は最終的に団体や支援活動に「寄付」されるため、募金は「寄付の手段」といえます。
そのため、寄付そのものが「差し出す行為」であるのに対し、募金は「お金を集める方法」に焦点があるという点が大きな違いです。
「義援金」は災害支援に限定された寄付金
「義援金」は、災害で被災した人や地域を支援するために集められるお金のことです。
地震や豪雨などの災害が発生すると、自治体や日本赤十字社などが義援金を募り、その全額が被災者の生活支援や地域復興に使われます。
一般的な寄付が幅広い活動に充てられるのに対し、義援金は「災害支援」という限定的な目的を持っているのが特徴です。
支援先や用途がはっきりしているため、寄付する側にとっても信頼性の高い仕組みといえます。
「寄贈」は物品を贈ること
「寄贈」は、お金ではなく物品を無償で提供することを指します。学校へ教材を寄贈する、図書館へ本を寄贈するなどが典型的な例です。
「寄付」は金銭を中心に、物品を含む広い概念であるのに対し、「寄贈」は物を贈る行為そのものに焦点がある点で異なります。
状況に応じて「寄付」と「寄贈」を使い分けることで、伝えたい内容がより正確に伝わるでしょう。
寄付には「お金」「物品」「労力」の3種類がある
「寄付」と聞くと真っ先に思い浮かぶのはお金かもしれませんが、それ以外にも物品や時間を役立てる形もあります。
お金に限らず多様な方法があるからこそ、誰にでも参加しやすいのが寄付の良さだといえるでしょう。
お金の寄付は最も一般的で幅広い支援方法
お金の寄付は、世界中で最も広く行われている社会貢献の形といえます。
募金箱に小銭を入れるといった身近なものから、NPOや医療機関、国際機関への継続的な支援、大口の寄付まで、規模や方法はさまざまです。
特定の活動や災害支援など「今すぐ力になりたい」と思ったときに実行できる即効性があり、少額でも多くの人が参加すれば大きな資金源となります。その結果、教育支援や医療活動、環境保全など幅広い分野を支える力となるのです。
お金の寄付は手軽に始められる点も魅力であり、寄付者にとって社会貢献の第一歩となりやすい方法だといえるでしょう。
物品の寄付は衣類や家具など不用品を活かせる
物品の寄付とは、家庭で使わなくなったものを社会で再利用する方法です。
代表的な不用品の例としては、着なくなった衣類、サイズが合わなくなった子ども服、買い替えで不要になった家具や家電、読み終えた本や使わなくなったおもちゃなどがあります。
これらは国内では福祉団体や児童養護施設、高齢者施設などで必要とされ、生活支援のために活用されるでしょう。また、海外では発展途上国に送られ、人々の暮らしを支える資源になります。
家庭の中で不要になった物を有効に循環させられるため、誰でも気軽に参加しやすい寄付の形だといえるでしょう。
時間や労力の提供も寄付のひとつ
寄付と聞くとお金や物を思い浮かべがちですが、自分の時間やスキルを提供することも大切な寄付の一種です。
地域の清掃活動に参加することや、登下校時の見守り活動、福祉施設の手伝い、地域の交流イベントの運営などの活動はすべて「労力の寄付」にあたります。
特に、自分の専門知識や経験を活かしたボランティアは、金銭以上の価値を生み出すこともあるでしょう。
例えば、医療従事者が災害支援に参加する、ITスキルを活かして非営利団体の運営をサポートするなど、多様な関わり方があります。
このように、お金だけでなく、自分の時間を少し提供するだけで社会の役に立てるのが大きな魅力です。
誰にでもできる身近な社会貢献の形として、時間や労力の寄付は今後さらに注目されるでしょう。
寄付をすると「寄附金控除」で税金の負担が軽くなる
寄付は社会を支える活動ですが、寄付をする人にとってもメリットがあります。
そのひとつが「寄附金控除」と呼ばれる税制上の優遇制度です。確定申告を通じて寄附金控除を申請すれば、支払った寄付金額の一部が所得税や住民税から差し引かれます。
ただし、どのような寄付でも控除が受けられるわけではありません。
控除の対象となるのは、国や地方公共団体、認定NPO法人、公益財団法人、社会福祉法人など、国が認めた団体に対する寄付に限られます。
街頭での募金や個人に直接渡したお金は対象外となるため、寄付を検討する際には寄付先が「寄附金控除の対象団体」かどうかを必ず確認することが重要です。
そして、控除を受ける方法もあらかじめ理解しておきましょう。
寄付後には領収書を受け取り、確定申告の際に添付する必要があります。控除の上限は個人の所得額によって異なるため、自治体や国税庁の公式サイトなどで詳細を確認しておきましょう。
また、近年多くの人が活用している「ふるさと納税」も寄附金控除の仕組みを利用した代表例です。
寄付した金額のうち自己負担2,000円を除いた分が控除され、さらに地域の特産品などのお礼の品を受け取れるため、仕組みを理解すれば賢く社会貢献に参加できます。
寄付は善意の行為であると同時に、制度を正しく活用すれば寄付する人自身の生活にとってもプラスになる点が魅力です。
参考:国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
お金以外の寄付も社会を助ける
寄付というと「お金を出すこと」というイメージが強いかもしれませんが、実際には金銭以外の方法でも社会貢献は可能です。
物品を活用した寄付や、自分の時間や労力を提供するボランティア活動など、多様な形があり、そのなかでも特に身近で取り組みやすいのが、家庭に眠る不用品を活かす「寄付」でしょう。
家の中で使わなくなった品を社会に循環させることで、処分する物が、誰かにとって大切な支援につながります。
不用品を寄付することで広がる社会貢献
日本で不要になったぬいぐるみや雑貨、衣類などは、海外に送られることで第二の役割を担います。
まだ十分に使えるぬいぐるみはアジアやアフリカの子どもたちの遊び相手や心の支えとなり、古着や生活用品は暮らしを支える必需品となるでしょう。
寄付できる品目は団体や仕組みによって異なり、衣類や本、家電など幅広く受け入れる場合もあれば、特定の物品に限定しているケースもあります。
そのため、自分が寄付したいものを適切に扱ってくれる支援先を選ぶことが重要です。
このような寄付は、現地の暮らしを支えるだけでなく、廃棄物を減らして環境保護にもつながります。
不要になった物が国境を越えて活かされることは、身近な行動が社会全体に広がる好循環を生み出す一例だといえるでしょう。
エコトレーディングが推進する寄付の仕組み
不用品を寄付して社会貢献をしたいと考えても、支援先は数多くあり「どこを選ぶべきか」と迷ってしまう方も多いでしょう。
そのようなときは、リサイクルショップ再良市場の輸出部門「エコトレーディング」におまかせください。
エコトレーディングでは、日本で不要になった品をフィリピンやタイのリサイクルショップに届け、現地の生活を支える取り組みを展開しています。
さらに、その売上の一部を現地の孤児院や国内のNPO団体に寄付する仕組みを整えていて、リユースを通じて環境保全と社会貢献の両立を実現していることが特徴です。
取り扱う品目は衣類やぬいぐるみ、おもちゃ、家具や家電、楽器、雑貨など幅広く、家庭で眠っているものが新たな価値を持つ形で活用されます。
身近な不要品を社会の役に立てられる方法として、エコトレーディングへの寄付をぜひご検討ください。
まとめ:「寄付」と「寄附」を正しく理解して行動につなげよう
「寄付」と「寄附」は意味に違いはありませんが、日常生活では「寄付」、公的な文書では「寄附」といったように、使われる場面によって表記が分かれます。
そして「寄付」と一口にいっても方法はさまざまで、お金だけでなく物品や時間の提供を通じて参加できることも大きな魅力です。
なかでも不用品を寄付する取り組みは、暮らしをすっきり整えると同時に社会を支える力にもなります。
家庭で眠っていた品が国内外で必要とする人の手に渡れば、生活の助けになるだけでなく、廃棄物削減や環境保全にもつながるのです。
このような不用品を活かした社会貢献を始めたい方は、再良市場の輸出部門「エコトレーディング」をぜひご活用ください。
まずは身近な一歩から、社会貢献の輪を広げていきませんか。