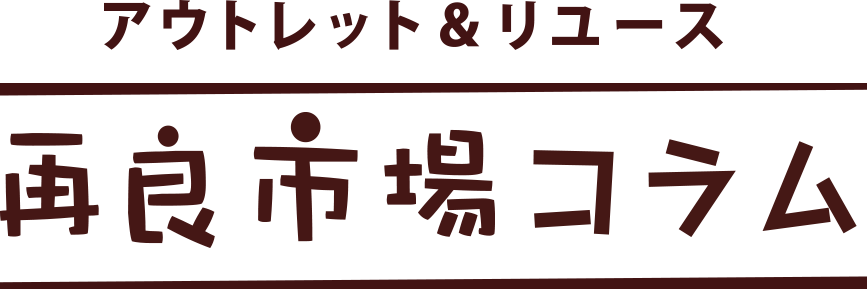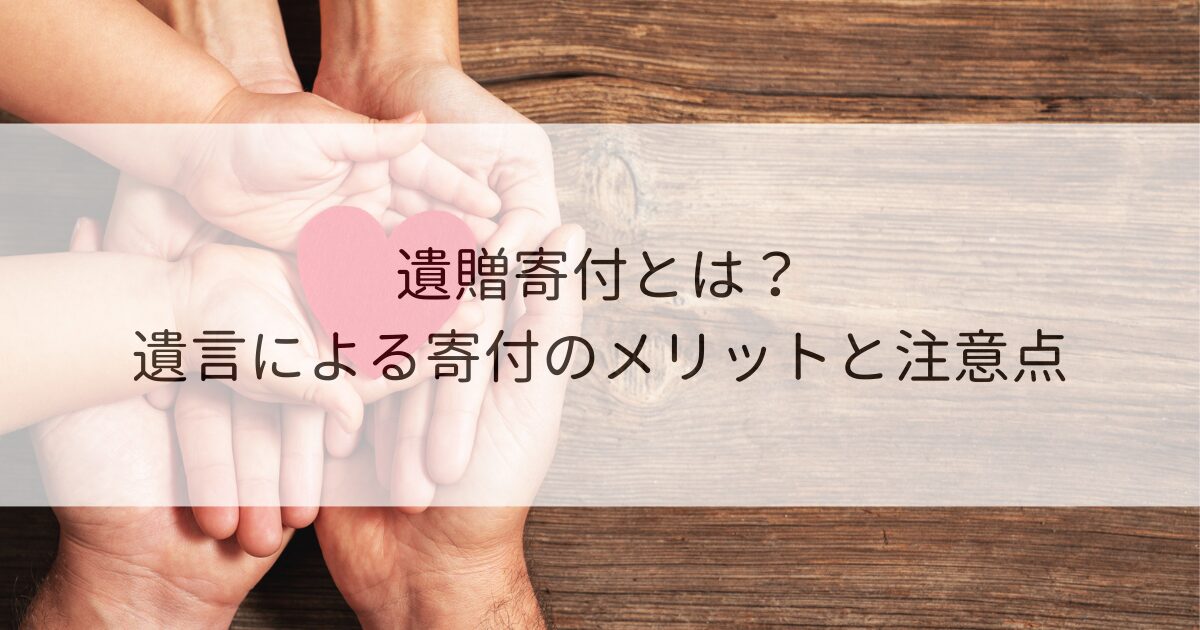「遺贈寄付」は、ご自身が亡くなったあとの財産を、公共団体や自治体などへ寄付する方法です。近年では、「自分の財産を好きなことに使いたい」「人生の最後に社会貢献がしたい」という想いから、この制度に関心を持つ方が増えてきています。
遺贈寄付を新聞やテレビで目にしたことがあるという方の中には、以下の疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
「寄付したい団体がいるのですが、どうしたらいいですか」
「遺贈寄付はいくらからできますか」
「遺贈寄付にはどんなメリットがある?」
この記事では、遺言による遺贈寄付の仕組みとメリットについて詳しく解説していきます。遺贈寄付をする上で、知っておくべき注意点についてもご紹介しますので、財産の使い道にお悩みの方はぜひご参考ください。
遺贈寄付は怪しい?安心して始めるための基礎知識
遺贈寄付に興味を持っているものの、「遺贈寄付って本当に安全なの?」と不安に思っている方もいるでしょう。そこでまずは、遺贈寄付を安心して始めるための基礎知識からご紹介していきます。
生前におこなう寄付との違いや、遺贈寄付を検討するベストなタイミングについても解説しますので、ぜひ知っておいてください。
遺贈寄付は遺言による自治体・活動団体への寄付
「遺贈寄付」とは、簡単に言うと死後に財産を寄付する制度のことです。遺言によって、家族(法定相続人)またはそれ以外の人に財産を譲渡することを「遺贈」といいます。遺言によって財産を譲る「遺贈」と、無償で送る「寄付」を組み合わせた言葉が「遺贈寄付」です。
遺贈寄付には3つの種類があります。
| 遺言による寄付 | 相続財産の寄付 | 契約による寄付 |
|---|---|---|
| 遺言で財産の一部または全部を民間非営利団体や自治体などに遺贈する | 手紙・言葉などで遺族に相続財産を遺贈する | 死後効力を発揮する贈与契約を締結する(生命保険信託など) |
遺贈寄付では、現金や預貯金のほか、さまざまな財産が対象になります。遺贈寄付を受け取った団体は、その資金や物品を資金や財産として活用し、社会貢献や地域支援に役立てる仕組みです。
遺贈寄付が広がりつつある背景と現状
近年、日本は高齢化の進行や社会貢献意識の高まりにより、遺贈寄付を検討する方がますます増えてきています。2025年は、団塊世代が75歳以上の後期高齢者枠になることから、人口の5人に1人が財産の行く先を考える時代になりました。
一般社団法人日本継承寄付協会が2024年に実施した実態調査では、70代の約84%が「遺贈寄付を知っている」と回答しており、高い認知度があることがわかっています。しかし、そのうちの約8割は「知っているが行動には移していない」という結果でした。
その理由は、「寄付したお金がどう使われるのかがわからない」「家族とのトラブルが不安」「遺贈寄付のやり方がわからない」といった内容です。遺贈寄付という制度があることは知っているが、仕組みまでは理解していないため、利活用に至らないという現状があります。
参照:【実態調査2024】「遺贈寄付、知ってはいるけど…」8割が実行に踏み切れない理由とは?|一般社団法人日本継承寄付協会
生前寄付との違い
遺贈寄付と一般的な寄付(生前寄付)の違いは、寄付するタイミングが「今」なのか「死後」なのかどうかです。生前寄付は生きているうちに寄付する方法ですが、自分の老後資金も確保しつつおこなわなければなりません。
一方、遺贈寄付は、遺言によって財産を寄付する方法なので、実際に寄付が実行されるのは亡くなった後です。生前の生活資金に影響がないことから、「老後の生活を守りつつ、最後に社会への恩返しがしたい」という方に選ばれています。
遺贈寄付を検討するベストなタイミング
遺贈寄付は、遺言書によって財産の寄付を取り決める方法です。そのため、遺言書を作成するタイミングよりも早い段階で検討しておくのがベストでしょう。一般的には、人生の節目となる出来事や、家族関係・財産状況に変化があったときにあわせて検討する方が多いです。
ただし、配偶者が亡くなった直後などは精神的な余裕がないことが多いため、あまり推奨されません。心身が健康なうちに「思い立ったタイミングで」検討するのが最善です。定年退職後など、ある程度生活が落ち着いて安定してきた頃がいいでしょう。
遺贈寄付における3つのメリット
遺贈寄付は、大切な意思を未来に託すための手段として注目されています。特に、子どもがいない方や、家族以外に財産を託したいと考える方にとっては、気になる選択肢の1つです。
遺贈寄付をおこなうメリットは、大きく3つあります。
- 財産の使い道を自分で決められる
- 相続税がかからない
- 老後の生活資金の心配がない
遺贈寄付と相続・生前寄付で迷っている方は、ぜひ比較するための判断材料としてお役立てください。
財産の使い道を自分で決められる
遺贈寄付のメリットとしては、まず財産の使い道を自分で決められることが挙げられます。単なる相続の整理ではなく、自分の生き方や信念を次世代に引き継げるのです。
遺贈寄付を受け付けている団体は、動物愛護や教育支援、医療研究などを掲げているものもあります。自分が共感できる分野を応援するために財産を使うことで、「亡くなった後も誰かの力になれる」という安心感や達成感が得られるのが魅力です。
相続税がかからない
遺贈寄付をおこなうことで、相続税が節税できるメリットもあります。一定の条件を満たす団体へ寄付をおこなうことで、相続税の課税対象から除外されるケースがあるのです。
相続税がかからない可能性がある団体には、以下の例があります。
- 自治体(国や地方公共団体)
- 特定の公益法人
- 認定されたNPO法人 など
つまり、本来であれば相続財産として税金が発生する部分を社会貢献に充てることで、税負担の軽減が叶います。相続人への遺産分配と遺贈寄付を組み合わせることにより、円満な相続も実現可能です。
老後の生活資金の心配がない
遺贈寄付は本人の死後に効力が発生することから、生前の生活資金を削る心配がないのもメリットです。普段の生活費や万が一のための医療費、介護費などをしっかり確保した上で、寄付の準備が進められます。
生前寄付だと、想像以上に長生きしてしまった場合の費用捻出に不安がありますが、遺贈寄付なら生きているうちは自由に財産を使えるのです。つまり、自分の人生を最後まで豊かに過ごし、残りの財産で社会の役に立てるという二重の安心感があります。
遺贈寄付できる財産の種類
遺贈寄付が可能な財産の種類にはさまざまなものがあります。ここでは、主な財産の種類を5つご紹介しますので、「どんなものが遺贈寄付できる?」と疑問に思っている方は、ぜひ参考にしてください。
- 現金・預貯金
- 家や土地などの不動産
- 株式・投資信託などの有価証券
- 貴金属・美術品・骨董品
- その他資産
現金・預貯金
遺贈寄付において、もっとも一般的で取扱いやすい財産が「現金・預貯金」です。まず、換金の手間がかからずそのまま団体や自治体に寄付できることから、受け取る側にも負担がありません。すぐに活動資金として活用できる点もメリットがあります。
さらに、現金は使い道の自由度が高く、活動資金や施設運営、支援事業などのニーズに応じた柔軟な利活用が可能です。預貯金であれば金融機関から手続きできるため、遺言書に「○○団体へ■■万円を寄付する」と記載しておけばスムーズでしょう。
家や土地などの不動産
遺贈寄付では、自宅や土地などの「不動産」も対象になるケースがあります。不動産は資産価値が高く、大きな社会貢献につながる可能性もあるでしょう。
不動産の遺贈寄付は、寄付先の団体によって有効な形に生まれ変わるのが特徴です。たとえば、土地を売却したお金を活動資金にしたり、建物をそのまま活動拠点として活用したりと、さまざまな活用方法があります。
ただし、不動産は現金よりも扱いが複雑なため、取り扱っている団体は非常に少ないのが現状です。相続人との調整や売却手続きの問題、売却せず活用する場合は維持管理の問題なども発生します。
不動産の遺贈寄付を検討している方は、まず専門家に相談してみるのがいいでしょう。
株式・投資信託などの有価証券
株式や債券、投資信託などの有価証券も遺贈寄付の対象です。有価証券は現金化しやすいため、資金として寄付先の団体が柔軟に活用できます。
ただし、証券会社を通じた手続きや、名義変更が必要です。市場で換金して資金化するケースと、配当・運用益を団体へ送付するケースがあります。
そのため、遺言書には具体的な証券の銘柄・数量などを明記しておくことが推奨されるでしょう。また、上場株式の場合、相場変動による評価額の変動にも考慮する必要があります。
貴金属・美術品・骨董品
高い資産価値のある動産も遺贈寄付の対象です。具体的には「貴金属・美術品・骨董品」などが該当します。売却して資金源となるのが一般的ですが、希少性によっては教育施設・博物館に寄贈され、展示・保存となるケースもあるでしょう。
ただし、換金や保管の手間がかかることから、受け入れ先の団体によっては事前に相談が必要です。特に、美術品や骨董品においては、専門的な鑑定と評価が求められるケースもあります。
遺言書に品目や特徴を明記しておき、寄付先の団体とも打ち合わせを済ませておくことで、スムーズに寄付できるでしょう。
その他資産
上記以外のその他資産や物品も、遺贈寄付できる場合があります。遺贈寄付できるその他資産の例は以下の通りです。
- 知的財産権(著作権・特許権)
- 特殊資産(船舶・農地など)
- 生命保険金や信託財産(契約による寄付)
- 車・家具・未使用の日用品など
ただし、受け入れが難しいものは寄付先が受け取らない可能性もあるため、十分注意しましょう。特に、管理が困難なものや真贋がわからないもの、流通市場のない物品などは断られる可能性が高いです。
遺贈寄付をおこなう手続きの流れ
遺贈寄付をおこなう手続きは、以下の流れでおこないます。
- 寄付の目的を考える
- 寄付先団体を選定する
- 専門家に相談する
- 公正証書遺言を作成する
- 家族へ説明する
- 亡くなった後の実行手順を決めておく
遺贈寄付をスムーズに進めるには、まず専門家や団体に相談して、寄付する財産と寄付先を決定することが大切です。家族間や相続人とのトラブルが不安な方は、専門家に相談する段階で早めに説明しておけるといいでしょう。
概要が決定した後は遺言執行者を指定し、法的に有効な遺言書の作成をおこないます。自身が亡くなった後は遺言執行者が遺言を開示して手続きを進め、遺贈が実現する形です。
遺贈寄付先の団体を選ぶコツ
遺贈寄付先の団体は、自分のニーズに合ったところを選ぶことが大切です。活動内容だけでなく、寄付が可能かどうかもしっかり見極めましょう。代表的な遺贈寄付先もいくつか紹介しますので、ぜひ選定時の参考にしてください。
寄付先団体の選び方
寄付先の団体を選ぶ際に着目すべきポイントは、以下の通りです。
- 活動内容が自分の信念や想いと一致しているか
- 財務状況や活動報告の透明性はあるか
- 自分が寄付したい財産の種類を受け付けているか
上記をチェックする際は、公式ホームページを参照するだけでなく、実際に活動現場に赴いて見学したり話を聞いたりして判断するのがいいでしょう。
また、寄付先団体には全国規模・地域密着型の違いもあります。「社会全体の課題解決に貢献したい」という方は全国規模、「地元のまちづくりに関わりたい」という方は地域密着型の団体がおすすめです。
【具体例】遺贈寄付先一覧
以下は、代表的な遺贈寄付先の一例です。
- 認定NPO法人 国境なき医師団日本
- 認定NPO法人 国際連合世界食糧計画WFP協会
- 公益財団法人 日本ユニセフ協会
- 認定NPO法人 ピースウィンズ・ジャパン
- 公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン など
上記以外にも、地元NPOや社会福祉法人など、さまざまな団体が存在します。市や町が管理する図書館・美術館・資料館への寄贈も1つの遺贈寄付の形です。
遺贈寄付をするときのデメリットと注意点は?
遺贈寄付は素晴らしい社会貢献の方法ですが、実行にあたってはいくつかの注意点があります。
- 相続人や遺留分の配慮をする
- 遺言書に不備がないか確認する
- 遺言執行者を決めておく
- 寄付先団体の信頼性や事情を確認する
上記4つの注意点とデメリットをしっかり把握し、事前に理解しておくことで、安心して手続きを進められるでしょう。
相続人や遺留分の配慮をする
遺贈寄付をおこなう際は、事前にしっかりと理由や想いを家族に説明し、理解を得ておく必要があります。自分の財産の一部またはすべてを寄付に回すことになるため、無断でおこなうと、相続人や家族とのトラブルに発展する可能性は否めません。
まずは、残されるであろう家族や相続人を第一に考えることが大切です。場合によっては、全額寄付するのではなく、一部を家族に残し、一部を遺贈寄付にするなどの配慮も必要になるでしょう。
遺言書に不備がないか確認する
遺贈寄付は遺言をもとに実行されるので、遺言書に記載ミスや漏れなどの不備があると無効になってしまいます。無効まではいかなくても、財産の特定が不十分であったり、寄付先の名称に誤りがあった場合は、関係者の間で解釈が分かれ、手続きが滞ってしまうでしょう。
そのため、法的な抜け漏れがないよう、公正証書遺言を利用して専門家のチェックを受けることが推奨されます。また、心身共に余裕があるときに作成することも大切です。
遺言執行者を決めておく
遺贈寄付をスムーズに進めるには、遺言執行者を事前に決めておく必要があります。執行者には、遺言による利害関係のない中立的な立場の第三者を選びましょう。弁護士や信頼できる専門家を執行者に選んでおけば、手続きの不備やトラブルも防いでもらえます。
執行者の指定がない場合は相続人に大きな負担がかかり、遺贈寄付が円滑におこなわれない可能性もあるため、十分注意してください。
寄付先団体の信頼性や事情を確認する
寄付先団体を選ぶ際は、活動内容や資金の使い道が明確かどうかを確認し、信頼性のある団体へと寄付することが大切です。財務状況や活動報告だけでなく、第三者放火などもしっかり見ておきましょう。
寄付先団体によっては、不動産の寄付が受けられない場合や、遺産の割合を指定して遺贈する「包括遺贈」が受けられない場合もあります。寄付先の事情もしっかり調べ、不明瞭な点があれば事前に相談してから決めてください。
まずは「エコトレーディング」を利用するのがおすすめ
ここまでは、遺贈寄付について紹介してきましたが、より手軽に自分の財産を未来に託す方法もあります。使わなくなったお気に入り品を寄付することで社会貢献につなげる、「エコトレーディング」を利用する新しい生前寄付の形です。
エコトレーディングは、不用品を送るだけでフィリピンやタイなどの途上国へ貢献できる仕組みを採用しています。エコトレーディングに寄付できる不用品の例は以下の通りです。
- ぬいぐるみ
- ランドセル
- ベビー用品
- 衣類・アクセサリー
- 食器・調理器具
- 電化製品・オーディオ
- 文房具 など
手間が少なく、送料の自己負担だけで寄付できるため、遺贈寄付を検討する初動としても始めやすいでしょう。社会貢献の仕組みも透明なので、安心して寄付できます。
エコトレーディングの公式サイトでは、寄付方法や対象品目の詳細もご案内しています。ぜひご参考ください。
まとめ:遺贈寄付で後悔のない資産の使い道を
遺贈寄付は、財産の使い道を自分自身で決められ、社会貢献に役立てる画期的な方法です。ただし、相続トラブルや受け入れ拒否などの問題が起こらないよう、しっかりと準備する必要があります。
「直接遺言にするほどではないけれど、身の回りの物を社会貢献に役立てたい」という方には、エコトレーディングへの寄付がおすすめです。(※エコトレーディングは弊社、(株)ウォーク 再良市場の輸出部門になります)
わたしたち再良市場には、買取や不用品回収における30年以上の実績がございます。タイ・フィリピン現地のリサイクルショップへ、寄付頂いたものとお客様の想いを大切にお届けいたしますので、ぜひお気軽にご利用ください。
まずはご自宅の不用品で、社会に想いをつなぐ一歩を踏み出してみませんか。