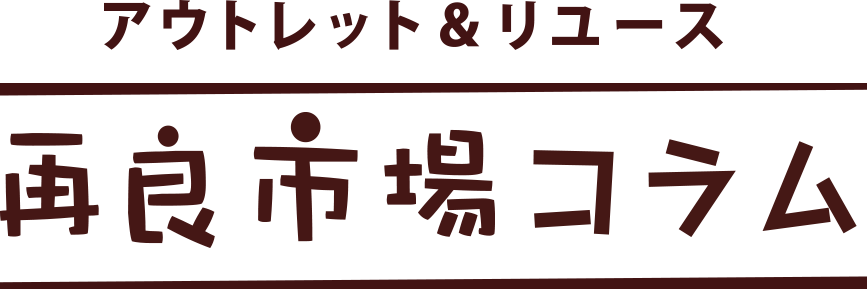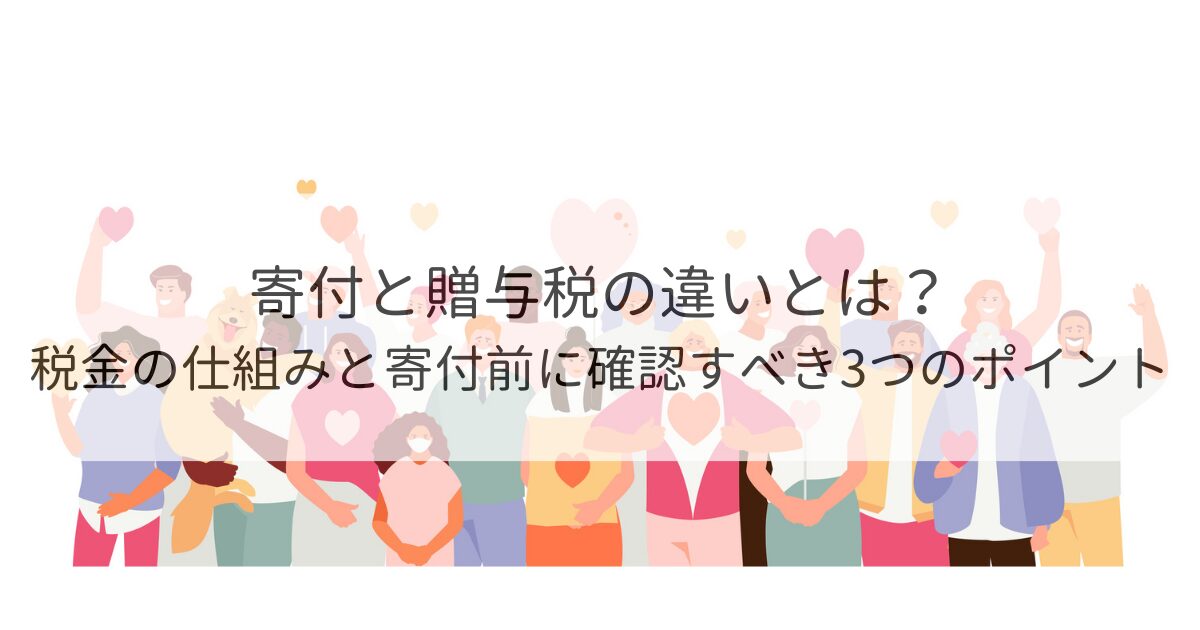「寄付」と「贈与税」の違いは?
「寄付をする場合に注意すべきポイントは?」
「信頼できる寄付先が知りたい」
社会貢献のために寄付をしたいと考えているけれど、寄付をすると税金が課税されるのか不安になる方もいるでしょう。寄付は金品だけでなく不要になった子どものぬいぐるみや衣類など、私たちの周囲にあるもので社会貢献ができます。
とはいえ、寄付の仕組みや注意点がわからず実際に行動に移せない方もいるのではないでしょうか。本記事では、寄付と贈与税の違いや、寄付をする前に確認すべき3つのポイントを解説します。寄付を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
「寄付」と「贈与税」の違いとは?それぞれの特徴を紹介
「寄付」と「贈与税」は物品や金品を渡すことに変わりませんが、内容や目的は大きく異なります。寄付と贈与税の違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 寄付 | 贈与(贈与税) |
|---|---|---|
| 意味 | 社会貢献のために金品を提供すること | 財産を無償で譲ること |
| 受け取る側の意思 | 不要 | 必要(贈与を承諾する必要がある) |
| 税金 | 原則非課税寄付金控除で所得税・住民税が軽減される場合あり | 贈与を受けた金額が一定額を超えると贈与税が課される |
寄付とは自分の意思で無償で物品や金銭を贈ること
寄付とは自らの意思で物品や金銭を提供することです。主に国や地方自治体、NPO法人などの団体に渡す場合が多く、社会貢献を目的としています。
以前は日本はアメリカなど他の国に比べると寄付の割合は低いと言われていました。寄付白書プラス2024によると、2011年の東日本大震災の年は約7割の人が寄付をしたことが明らかになっています。2011年以降も寄付の割合は増えており、災害や社会課題への関心の高まりが、増加につながっていると言えるでしょう。
参考:寄付白書プラス2024
贈与税とは個人間で財産を贈与した場合に課される税金
贈与とは、自分の財産を相手に譲りたいという意思を示し、相手が承諾することで成立する契約の一種です。贈与税は、贈与された財産の金額に応じて課される税金を指します。贈与は個人同士、または法人を相手に行われることが一般的です。
一方、寄付は相手の承諾がなくても、自分の意思で物品や金銭を提供できる点が特徴と言えます。贈与と寄付は、意思の承諾の有無や課税の仕組みなど、性質が大きく異なる点を知っておきましょう。
個人が寄付する場合にかかる税金と控除の仕組み
個人が寄付をする場合、大きく分けて法人や非営利団体、同族会社、営利団体、個人などの寄付先があります。寄付先によって税金や控除などの対象が異なるため、寄付をする前に確認しておきましょう。
個人から法人へ寄付 | 寄付金控除が適用されるケース
個人から法人への寄付は、国や自治体に寄付するケースが当てはまります。特定寄付金に指定されている団体に寄付をすると、所得控除の対象になる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
特定寄付金は公益社団法人や公益財団法人、認定NPO法人などが該当します。詳しくは国税庁のホームページにて確認してください。
寄付金控除を受ける場合は確定申告が必要です。特定寄付金の合計額は、総所得金額等の40%相当が上限となっており、全額が寄付金の控除となるわけではありません。寄付金控除には「税額控除」という仕組みがあり、実際に差し引くことが可能なのは、所得税額の25%までとなっています。
参考:国税庁ホームページ
個人から非営利団体へ寄付 | 所得控除が受けられるケース
個人から非営利団体へ寄付する場合、非課税で扱われることが一般的です。特定認定NPO法人への寄付は、所得控除または税額控除を選択できる仕組みがあります。一方、都道府県や市町村が認定したNPO法人に寄付した場合、寄付金税額控除の対象になる点を押さえておきましょう。
ただし、控除を受けるには確定申告を行う必要がある点には注意が必要です。あらかじめ寄付先が認定NPO法人であるかどうかを確認してください。認定の有無は内閣府のNPO法人ページにて確認できます。
個人から同族会社や営利団体へ寄付 | 法人税の課税対象
個人が同族会社や営利団体に寄付した場合、法人税が課されます。同族会社とは、株主が3人以下で、株主間が親族など特別な関係にある個人や法人が議決権の過半数を超える会社のことです。
個人が同族会社へ寄付した場合、受け取り側は寄付金を収益として計上するため、法人税課税所得に含まれます。
営利団体とは、利益を株主や社員に分配することを目的としている組織のことです。株式会社や合同会社などが該当します。営利団体も同族会社同様、個人から寄付を受け取ると、法人税の課税対象となる点が特徴です。
個人が同族会社や営利団体へ寄付した場合は、原則として寄付金控除の対象とはならない点にも注意しましょう。営利や私的利益に使われる可能性のある寄付は対象外とされているためです。
個人から個人へ寄付した場合 | 110万円を超えると贈与税の対象
個人から個人へ金銭や財産を提供する場合、寄付と呼ばれることがありますが、税法上は贈与税の課税対象です。税金は贈与を受けた側にのみ課されます。贈与税は、1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産について税務署に申告・納付が必要です。
ただし、年間110万円以内であれば贈与税は課されません。110万円を超える贈与を受けた場合は、基礎控除額を差し引いた金額に贈与税がかかります。贈与を検討する際は、年間110万円を超える場合の税額や申告の手続きもあわせて確認しておくと安心です。
参考:国税庁ホームページ
贈与税の計算方法 | 暦年課税と相続時精算課税の違い
相続税の計算方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。特徴や計算方法は以下のとおりです。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 対象者 | 贈与を受けた人 | 60歳以上の直系尊属から18歳以上の子・孫 |
| 仕組み | 1年間(1/1〜12/31)にもらった財産の合計額に基づき課税 | 贈与時に一律20%で課税し、将来の相続時に精算 |
| 非課税 | 110万円/1年間 | 2,500万円(特別控除)まで非課税 |
| 申告 | 110万円を超えた場合申告 | 非課税枠を超えた分のみ申告 |
| 選択の可否 | 常に暦年課税 | 一度選択すると暦年課税に戻せない |
暦年課税|基礎控除は110万円で超えた金額に対して課税額を計算する方法
暦年課税とは、贈与税の課税方法の一つで、その年の1月1日から12月31日までに受け取った財産の合計額に基づき計算されます。暦年課税の対象は贈与を受けた人であり、贈った人には課税されません。
贈与税には「基礎控除額」という制度があり、110万円以下の場合は課税されない点が特徴です。暦年課税は贈与された金額のうち110万円を超えた金額に対して課税されます。基礎控除は受け取った人ごとに適用されることも押さえておきましょう。
参照:国税庁ホームページ
相続時精算課税|贈与時に税額を確定し、相続時に精算する方法
相続時精算課税は、親や祖父母など60歳以上の直系尊属(※1)から贈与を受ける場合、18歳以上の子や孫が利用できる制度です。相続時精算課税は控除額を超えた分だけ贈与税がかかり、将来相続が発生したときに贈与時に支払った税金と相続税を調整します。
贈与を受けた初年度は、翌年の2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出することが必要です。一度「相続時精算課税」を選択すると、暦年課税に戻せません。
相続時精算課税では、贈与を受けたときに一律20%の税率で贈与税を計算します。2024年の改正により、年間110万円までの基礎控除も利用できるようになりました。加えて、従来からある特別控除として2,500万円まで非課税で贈与できる枠があります。(※2)親や祖父母から子や孫への生前贈与を一定額まで非課税とする制度上の控除です。
控除の範囲内であれば贈与税はかからないことも理解しておきましょう。
※1 直系尊属とは、自分から見て上の世代にあたる血縁者のことです。 具体的には、親や祖父母など、自分の先祖にあたる人を指します。
寄付金控除の制度と活用方法
寄付金控除は、個人が国や地方団体、公益財団法人などに寄付を行った際に、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。社会貢献をしながら税金の控除を受けられるため、寄付を考えている方にとって有益な仕組みと言えます。
個人が地方自治体などに寄付した場合の寄付金控除
個人が国や地方団体、公益財団法人などに寄付を行った場合、確定申告をすることで、所得税や住民税の控除を受けられます。控除の対象となる金額は、総所得金額の最大40%が目安です。寄付金控除を受けるには、寄付先から受け取った領収書を確定申告書に添付する必要があります。
制度を上手に活用して、社会貢献と節税を実現しましょう。
参考:国税庁ホームページ
寄付金控除を申請する流れ
寄付金控除を申請する流れは以下のとおりです。
- 寄付をする
- 寄付をした相手から領収書を受け取る
- 確定申告をする
まずは自治体や認定NPO法人など、寄付控除の対象となる団体に寄付を行います。寄付の支払い方法は、現金・振込・クレジットカードなどから選ぶことが可能です。寄付後は証拠として寄付先から領収書を受け取りましょう。翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行います。
申告書に寄付先や寄付額を記入し、領収書を添付してください。税務署から確認を求められた場合に備えて、5〜7年間は自宅に大切に保管しましょう。
寄付前に確認すべき3つのポイント
寄付前に確認すべき3つのポイントは以下のとおりです。
- 信頼できる寄付先を見つける
- 活動内容を確認する
- 寄付先が寄付金控除の対象か確認する
寄付の確認を怠ると「思っていた活動に使われなかった」「控除を受けられなかった」といった後悔につながる可能性があります。
信頼できる寄付先を見つける
寄付をする際には、信頼できる寄付先を選ぶことが大切です。エコトレーディングは、不要になったものを送るだけで子どもたちの笑顔につながる不用品回収型の社会貢献サービスです。自宅で眠っているものが、誰かの喜びに変わる仕組みが整っています。
直接持ち込みや郵送も可能で、事前連絡も不要なため、自分の都合に合わせて気軽に支援できる点も嬉しいポイントです。発送方法や受付できないものの詳細は、エコトレーディングのホームページをご確認ください。
活動内容を確認する
寄付先を検討する際には、団体の活動内容をしっかり確認することが大切です。特に、団体の活動理念や活動報告など、寄付金の使用用途が明確に公表されているかをチェックしましょう。
ホームページやSNSなどに最新情報が定期的に更新されているかも確認してみてください。実際に寄付を行った人の口コミやレビューを参考にするのも良い方法です。代表者やスタッフの顔写真が掲載されている場合、団体の雰囲気や信頼性を把握しやすくなります。
最終的には、自分が「活動を応援したい」と思える内容であるかを見極めたうえで寄付先を決めるようにしましょう。
寄付先が寄付金控除の対象か確認する
寄付金控除は、1年間に寄付した合計額が2,000円を超えた部分(※)に対して、所得控除や税額控除を受けられる制度です。控除の対象となる寄付先は、国や地方公共団体、認定NPO法人、公益財団法人などに限られます。
寄付を行う前には、寄付先が控除の対象団体であるかどうかを必ず確認しましょう。寄付先の公式サイトや内閣府NPOホームページなどを利用して確認すると安心です。
※参考:国税庁ホームページ
まとめ:寄付・贈与前に税金と手続きをチェックしよう
寄付と贈与は、いずれも金品などを誰かに渡す点では似ていますが、目的や税金の仕組みが大きく異なります。寄付は社会貢献を目的としており、団体によっては寄付金控除や所得税などの控除が受けられる点が特徴です。
一方、個人間の贈与は原則として贈与税の対象となります。ただし、年間110万円までの基礎控除の範囲内であれば非課税です。
寄付を行う際は、事前に以下の3点を確認しましょう。
- 信頼できる団体か
- 活動内容が明確であるか
- 控除対象の寄付であるか
ポイントを確認したら、気になる団体の公式サイトや認定団体リストをチェックして、自分が支援したい活動を選んでみましょう。
寄付先に迷ったらエコトレーディングがおすすめです。ぬいぐるみや日用品を段ボールに詰めて送るだけで、アジアの子どもたちへの支援につながります。家庭にある不用品を寄付することで、簡単に社会貢献ができる点も魅力です。活動内容は公式ホームページから確認できるため、安心して利用できます。エコトレーディングは、どの団体に寄付をしていいのか迷っている方にぴったりのサービスです。
小さな一歩でも、あなたの寄付が誰かの笑顔につながります。